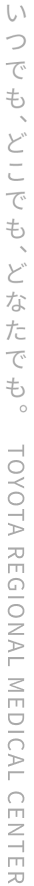診療サポート部門
診療放射線科

安心で確実な検査と正確な画像診断で、的確な治療方針についてのアドバイスを行っています。
概要
診療放射線技師22名(男性13名、女性9名)、検査補助者4名のスタッフで、主にX線を利用した検査を行っています。
救急、外来、入院、在宅患者さまの検査だけでなく、地域医療連携室からの他医療施設依頼検査も行っています。健診では、総合健診、法定健診、学校健診など幅広い業務を行っています。
救急、外来、入院、在宅患者さまの検査だけでなく、地域医療連携室からの他医療施設依頼検査も行っています。健診では、総合健診、法定健診、学校健診など幅広い業務を行っています。
特徴
X線CT検査では、管球一回転で最大640枚の画像が取得できる320列デュアルエナジーCT(スペクトラルシステム対応)を用いて、従来のCTでは撮影できなかった心臓の血管などを撮影する冠動脈CT検査などを行っています。またCTを利用した肺ドックや大腸CT検査の低被ばく化にも積極的に取り組んでいます。
1.5T(テスラ)の超電導MRI装置については、放射線被ばくが無い利点を生かし、脳ドックをはじめ骨や関節の疾患、がんなどの幅広い疾患の検査を行っています。
健診では、胸部X線撮影、胃部X線撮影、マンモグラフィを行い、がんの早期発見に日々取り組んでいます。
また在宅患者さまに対する在宅ポータブル撮影を積極的に行っています。
1.5T(テスラ)の超電導MRI装置については、放射線被ばくが無い利点を生かし、脳ドックをはじめ骨や関節の疾患、がんなどの幅広い疾患の検査を行っています。
健診では、胸部X線撮影、胃部X線撮影、マンモグラフィを行い、がんの早期発見に日々取り組んでいます。
また在宅患者さまに対する在宅ポータブル撮影を積極的に行っています。
施設・設備
主な医療設備
1.5T(1テスラ=10,000ガウス)MRI装置
従来の装置に比べ解放感があり、閉所恐怖症の方にも検査が受けやすくなりました。
320列デュアルエナジーX線CT装置(スペクトラルシステム対応)
最短0.275秒で撮影が可能に
最新AI技術により、最大80%以上の被ばく低減を実現
外科用移動型X線TV装置
X線TV装置(6台)
X線乳房撮影装置(2台)
X線一般撮影装置(4台)
骨塩量測定装置(全身用・前腕用) 3台
胸部X線検診車(2台)
放射線画像管理システム
3次元画像処理装置(2システム)
パノラマX線撮影装置
在宅X線撮影装置(2台)
資格・認定
施設認定など
- 日本脳ドック学会認定施設
- マンモグラフィ検診施設画像認定施設
- 全衛連エックス線写真精度管理調査 評価A
- 画像診断管理認証施設
認定技師
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 放射線管理士 | 2名 |
| 放射線機器管理士 | 2名 |
| 胃がん検診専門技師 | 6名 |
| 検診マンモグラフィ撮影技師 | 4名 |
| 骨粗鬆症マネージャー | 2名 |
| 磁気共鳴(MR)専門技術者 | 1名 |
| X線CT認定技師 | 1名 |
| 肺がんCT検診認定技師 | 2名 |
| 医療画像情報精度管理士 | 1名 |
| 血管診療技師(CVT) | 1名 |
| 乳房超音波認定技師 | 1名 |
| 超音波検査士(体表) | 1名 |
| 超音波検査士(消化管) | 1名 |
実績
検査実績
| 検査名 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|
| 一般撮影検査 | 10,537件 | 7,986件 | |
| 在宅撮影 | 150件 | 177件 | |
| CT検査 | 診療 | 7,171件 | 6,042件 |
| 検診 | 381件 | 382件 | |
| MRI検査 | 診療 | 1,983件 | 1,722件 |
| 検診 | 1,224件 | 1,219件 | |
| 乳房X線検査 | 診療 | 90件 | 72件 |
| 検診 | 5,564件 | 5,465件 | |
| 骨塩定量検査 | 診療 | 370件 | 271件 |
| 検診 | 2,577件 | 2,652件 | |
| 院内で行っている検診 | 胸部X線 | 37,841件 | 37,765件 |
| 頸椎 | 1,244件 | 1,219件 | |
| 胃部X線 | 20,219件 | 21,403件 | |
| 院外で行っている検診 | 胸部X線 | 19,229件 | 19,787件 |
| X線テレビ撮影・透視検査 | 255件 | 218件 | |
学会発表実績
| 学会名 | 主な発表演題 | 累計発表演題数 |
|---|---|---|
| ECR (European Congress of Radiology:欧州放射線学会) | Usefulness of multidetector CT(MDCT)in lung screening | 1演題 |
| ISRRT世界大会(世界放射線技師会世界大会) | Helical scanning on patients who are unable to Hold Their Breath | 1演題 |
| 日本放射線技術学会総合学術大会 | A study of the characteristics of automatic exposure mechanism About influence by the difference between setting SD value and phantom | 11演題 |
| 日本放射線技術学会秋季学術大会 | ヘリカルピッチ及びZ軸フィルター厚の違いによる実効スライス厚の変化 | 1演題 |
| 日本CT検診学会 | 受診者被曝低減と時間分解能向上を両立させる肺がんCT検診撮影法の基礎的検討 | 3演題 |
| 日本放射線技師会総会 | 在宅医療現場に診療放射線技師が加わった事が大きい | 2演題 |
| 日本放射線技術学会 中部部会(東海支部含む) | 安静呼吸時のヘリカルスキャンの検討 -体軸方向空間分解能について- | 4演題 |
専門誌掲載
- 日本放射線技術学会誌
- メディカルレビュー
- Rad Fan
- 日本CT検診学会誌
学術論文(査読有 論文)
- 受診者被ばく低減と時間分解能向上を両立させる肺がんCT検診撮影法の基礎的検討 (査読有 原著論文)日本CT検診学会誌 21巻2号
- CT自動露出機構(CT-AEC)の性能特性-低線量肺がんCT検診利用を想定した特性評価 (査読有 原著論文)日本CT検診学会誌 22巻2号
- 「位置決め画像」撮影による被ばくについての基礎的検討 ー肺がんCT検診での受診者被ばくに与える影響についてー(査読有 原著論文)日本CT検診学会誌 26巻2号
- Effect of blue light from LCD on VDT work : Experiment using blue light reduction function LCD (査読有 原著論文)JOURNAL OF THE SOCIETY FOR INFORMATION DISPLAY28巻8号691-697
その他
対外学術講演
- 日本放射線技術学会 中部部会 CT研究会
- 三重胸部CT技術研究会
- 岐阜CT研究会
- 中部東芝CTユーザー会
- 西三河放射線技師会
- 在宅支援WEBセミナー
- 在宅医療の相棒セミナーSeason2
受賞
- 画論 The Best Image2013 テクニカル賞